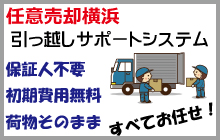不動産相続で後悔しないための基礎知識
はじめに
親が亡くなり、相続の話が持ち上がるとき、多くの方が最初に直面するのが「実家(不動産)をどうするか?」という問題です。
現金や預貯金の相続とは違い、不動産は分けることができません。また、固定資産税や管理の手間、売却や活用の手続きなど、知識がないとトラブルや損失に直結します。
この記事では、不動産を相続したときに起こりがちな問題と、その解決策について、実例を交えてわかりやすく解説します。
相続した実家、あなたはどうしますか?
親が亡くなったあと、空き家となった実家を相続する人は少なくありません。ところが、相続したあとどうすればいいのか、明確な答えを持っていない方が大半です。
選択肢としては主に以下の3つがあります:
- 住む(自分または家族)
- 貸す(賃貸として活用)
- 売る(現金化する)
それぞれにメリット・デメリットがあるため、家族構成や資産状況、立地などによって最適な選択肢は変わります。
事例①:空き家を放置して思わぬ出費に
千葉県に住むCさんは、母親が亡くなり、都内の実家を相続しました。当面は使う予定がなかったため、「とりあえずそのままにしておこう」と放置。
しかし1年後、近隣住民から「雑草がひどく、害虫が出ている」との苦情が入りました。行政からも是正勧告があり、慌てて除草や修繕を実施。さらに、空き家であっても毎年の固定資産税が発生し、数十万円の出費に。
結局、その後に売却しましたが、空き家期間が長かったために建物の劣化が進み、想定よりも安い価格での取引となりました。
教訓:
不動産は「相続した時点で責任が発生する」ことを忘れず、放置せず早期に方針を決めましょう。
事例②:兄弟で揉めた「分けにくい不動産」
Dさんは父親から実家を兄弟3人で相続しました。ところが、1人は住み続けたい、もう1人は売って現金化したい、Dさん自身は貸したいと主張がバラバラ。
結果として意見がまとまらず、話し合いが長期化。最終的には家庭裁判所での調停となり、関係が悪化してしまいました。
教訓:
不動産は「分けられない資産」です。遺言や生前の話し合いがなければ、相続人同士でのトラブルの火種になります。早めに専門家を交えて調整を。
売却を選ぶ場合のポイント
「もう誰も住まない」「遠方で管理ができない」「売って分けたい」という場合、不動産の売却は現実的な選択です。
ただし、以下の点に注意が必要です:
- 名義変更(相続登記)が完了していること
- 複数の相続人が同意していること
- 建物の状態を把握しておくこと(劣化や未登記増築など)
売却には時間がかかる場合もあるため、早めに専門家に相談することでスムーズな取引が可能になります。
もし売りたくない場合はリースバックや賃貸活用も
「想い出のある家を残しておきたい」「いずれ子どもが使うかもしれない」という理由で売却をためらう方には、リースバックや賃貸活用といった選択肢もあります。
リースバックとは?
自宅を不動産会社などに売却し、そのまま賃貸として住み続ける仕組み。高齢者の生活資金確保にも使われていますが、相続人が住むケースでも有効です。
また、空き家バンクや定期借家契約を活用すれば、古い家でも賃貸として収益を生むことも可能です。
相続前にやっておくべき3つの準備
将来的に親の不動産を相続する可能性がある方は、次の3つを事前に行っておくことで、トラブルや損失を大きく減らせます。
- 親とのコミュニケーションを取る(意思確認と資産把握)
- 遺言書や遺産分割協議書の準備を促す
- 不動産の状態や相場を事前に調べておく
特に親が高齢な場合、「元気なうちに話しておけばよかった」と後悔するケースは非常に多いです。
まとめ:相続は“人と不動産”の問題
不動産相続は、単なる財産分与の話ではありません。家族関係や暮らし方、感情や記憶が絡み合う、非常に繊細なテーマです。
その分、正しい知識と冷静な判断、そして早めの準備が、将来の安心につながります。
私たちは、不動産に関する相続・売却・活用のご相談を幅広くお受けしています。
「この家、どうすればいい?」と迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
#相続 #不動産売却 #空き家